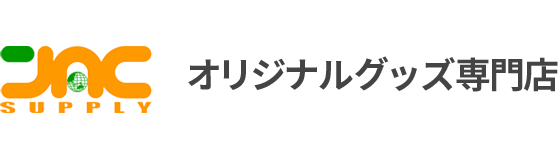工場でオリジナル製品を大量に作るときに「大ロット生産」という言葉が使われます。この大ロット生産とはどういう意味なのか、逆の意味にあたる小ロットとの違い、大ロット生産に向いているグッズなど、大ロット生産に関する諸々の疑問を解説します。
目次
大ロット生産とは?
大ロット生産とは同種の製品を一度に大量生産することです。ロットとは生産する際の単位で数が多いと大ロット、数が少ないと小ロットといった使い方をします。大ロット生産をすることにより「コストダウン」「品質の均一化」などのメリットがあります。

ロットとは?
ロットとは同種の製品を生産する際の最小単位のことです。英語で書くと「Lot」で、「ひと組」「ひと山」という意味があります。
たとえば、1ロット100個といった場合、その製品は「100個から生産できる」という意味であり、同時に「100個未満では生産しない」ということを意味します。この場合、1ロット注文すると100個、10ロット注文すると1,000個の製品が納品されます。発注する側からすると1ロットあたり何個なのか把握しておかないと、必要以上に納品されてしまうので注意が必要です。基本的に、1ロットをいくつにするかは生産する側が決め、工場の規模に比例して1ロットあたりの数量も多くなる傾向があります。
ロット管理のメリット
オリジナルグッズの生産におけるロット管理の最大のメリットは、品質と納期の安定を確保できる点にあります。ロットごとに原材料や印刷機の設定、製造日などを記録しておくことで、仕上がりのばらつきを防ぎ、再注文時にも同等品質で再生産することが可能になります。特に印刷やカラー再現が重要なグッズでは、ロット単位の記録が品質維持に欠かせません。また、万一不良品や色ズレなどのトラブルが発生した場合も、どのロットで問題が起きたのかをすぐに特定でき、再発防止や迅速な対応につなげられます。
さらに、在庫や納品スケジュールの管理にも有効です。ロットごとに生産・入庫・出荷を把握することで、在庫過多や納期遅延を防ぎ、効率的な生産計画が立てやすくなります。キャンペーンやイベント向けに短期間で大量生産する場合でも、ロット単位での進捗管理により全体の流れを可視化できます。結果として、クライアントとのやり取りや品質保証を含む生産体制全体の信頼性が向上し、リピート受注やブランド価値の向上にもつながります。

大ロット生産の特徴
では大ロット生産をするとどんなよいことがあるのでしょうか。一番のメリットは安く作れるということです。たとえばネックストラップを5,000本と50,000本生産する場合、一度に5万本まとめて作ったほうが時間短縮となり1本あたりのコストが安くなります。また、生産工程(紐の染色、印刷、検品、梱包など)を単純化・細分化することにより生産性も向上します。さらに生産工程を単純化・細分化したことにより、作業者のスキルに依存する工程がなくなり、均一な品質の製品を生産できるようにもなります。

大ロット生産の起源
大ロット生産(ライン生産)の起源は諸説ありますが、1801年にマーク・イザムバード・ブルネルがイギリス海軍用に滑車の生産法を確立したことから始ったとされており、その後、1914年にフォード社のハイランドパーク工場内にベルトコンベアが導入されたことで基本形が完成されました。フォード社は製品の標準化(車種をひとつに絞る)、部品の規格化(部品の形、大きさを統一する)、製造工程の細分化(流れ作業化)を行い生産台数を飛躍的に向上。当時1000ドルした自動車は300ドルまで価格を下げることに成功し多くの人が自動車を持てるようになりました。
このフォードのシステムは「フォーディズム(Fordism)」と呼ばれ、現代の大ロット生産やオートメーション化の基礎となりました。その後、この考え方は家電、衣料、食品などさまざまな分野に広がり、第二次世界大戦期には兵器や物資の大量生産にも応用されます。戦後、日本企業もこの手法を取り入れ、トヨタ生産方式(Just In Time)など、効率と品質を両立させた改良型システムへと発展していきました。
英語・中国語で「大ロット生産」は何と呼ぶ?
大ロット生産は英語で「Mass Production」と呼ばれます。これは、大量に、連続的に生産することを指し、標準化された製造業で広く使われる言い回しです。また、「Large-scale Production(大規模生産)」とも呼ばれることもあり、この場合は量だけでなく設備や工程の規模が大きいことを強調します。
中国語では「大批量生产」「大规模生产」といった呼び方をします。前者は一般的な表現で、「ロット生産」や「バッチ生産」のうち大量の場合に使われます。後者は「大規模生産」という意味で、英語の「Large-scale Production」と同様に、規模が大きいことを強調します。
海外で大ロット生産が可能な工場をお探しの場合は弊社にてサポートいたしますので、ぜひ一度メールフォームからお問い合わせください。
大ロットと小ロットの違い
大量に生産することを大ロット生産、少量のみ生産すること小ロット生産と呼びますが、同じ製品を小ロットと大ロットで注文した場合、どのような違いがあるのか具体例を挙げて解説します。
納期の違い
納期は大ロット生産時のほうが小ロット生産時よりも長くかかります。たとえば、弊社のネックストラップの場合、100本注文時の納期は35営業日(試作10営業日+量産25営業日)ですが、50,000本注文時の納期は45営業日(試作15営業日+量産30営業日)ほどかかります。注文数による納期の変化の幅は、商品の種類や印刷方法によって異なります。
単価の違い
商品単価は大ロット生産時のほうが小ロット生産時よりも安くなります。弊社のネックストラップSN10Lを例にすると、
100本注文時の1本あたりの単価は332円ですが、1,000本注文時の単価は136円と、半額以下まで下がります。これは一度に大量に生産したほうが時間も手間もかからないため、人件費および時間的なコストが削減でき、単価を低く抑えられるということです。社員用のネックストラップであれば、数年先の分までまとめて注文するなどして、なるべく本数を多くしたほうがお得に生産できます。
生産場所の違い
大ロット生産をするには大規模な工場が必要であるため、たくさんの土地、設備、スタッフが必要です。土地の価格や人件費を考えた場合、日本よりも安い海外の工場で大ロット生産を行うのが一般的です。ひと昔まえは海外工場といえば中国でしたが、経済の発展にともない人件費も高騰したため、現在ではタイやベトナムなどの、より人件費の安い国に工場を構える企業が増えています。

大ロット生産のメリット・デメリット
大ロット生産のメリット
- 単価を大幅に抑えられるため、販売用や大規模イベント向けにコスト効率が高い。
- 一度に大量に生産することで、仕上がりの品質や色味のブレを減らしやすい。
- 生産ラインをフル稼働できるため、納期の見通しを立てやすく、安定した供給が可能。
大ロット生産のデメリット
- 初期費用や在庫リスクが大きく、売れ残りや保管コストが発生しやすい。
- デザイン変更や仕様修正が難しく、柔軟な対応がしにくい。
- 少量販売やテストマーケティングには不向きで、需要予測を誤ると損失につながる。
小ロット生産のメリット・デメリット
小ロット生産のメリット
- 少量から試作や販売が可能で、新デザインのテストや限定品企画に適している。
- 在庫リスクが小さく、トレンドや顧客の反応に合わせた柔軟な対応ができる。
- 改良や仕様変更を繰り返しやすく、品質向上のための検証が行いやすい。
小ロット生産のデメリット
- 生産コストが高く、1点あたりの単価が上がりやすい。
- 生産効率が低く、納期が長くなる場合がある。
- 大量発注に比べて工場の生産優先度が下がることがあり、スケジュール調整が必要になる。
大ロット生産に適した商品は?
大ロット生産のほうが小ロット生産よりも安い単価で作れるということがわかりました。では大ロット生産に適した商品、逆に適さない商品とはいったいどんなものなのでしょうか。商品と使い方も合わせて紹介します。
大ロット生産に適した商品
大ロット生産に向いているのは、需要が安定しており、長期的に一定数以上の販売が見込める商品です。たとえば企業やイベントで配布されるノベルティグッズ、定番のスマホアクセサリー、キャラクターグッズなどが該当します。大量生産により単価を大幅に下げられるため、コストパフォーマンスに優れています。また、製造ラインを効率化でき、品質の均一化も図りやすい点が特徴です。ただし在庫リスクを抱えるため、需要予測と販売計画の精度が重要になります。
- 需要が安定している商品
- 定番品・人気シリーズなど、年間を通して一定の販売量が見込める商品。
- 仕様変更の少ない商品
- 一度デザインや仕様が確定すれば、長期的に同じ形で販売できるもの。
- 印刷位置や素材が固定されている商品は大量生産に向く。
- 単価を下げたい商品
- 販促用・ノベルティ・OEM供給など、コスト重視で生産効率を優先するケース。
- 大量発注により1点あたりの単価が大幅に下がるため、利益率を高めやすい。
大ロット生産にオススメの商品
1,000個以上作る場合、1個あたりの単価100円以下で注文できます。
大ロット生産に適さない商品
一方、小ロットやオーダーメイド向けのアイテムは大ロット生産に適しません。流行やシーズンによってデザインが頻繁に変わるグッズ、限定販売を目的とした商品、個人の好みに応じたカスタマイズ品などがその代表です。これらは市場の変化に柔軟に対応する必要があるため、大量生産では在庫過多や廃棄リスクを招きやすくなります。少量で試作・販売し、反応を見ながら改良を重ねる方が効率的なケースが多いのが特徴です。
- デザインや仕様が頻繁に変わる商品
- 季節限定・トレンド商品・コラボ企画など、短期間で入れ替わるアイテム。
- 需要予測が難しい商品
- 新規ブランドや初回販売品など、どの程度売れるか見通しが立たない場合。
- 保管コストや劣化リスクが高い商品
- 賞味期限のある食品や、湿気・紫外線で劣化しやすい素材を使うグッズなど。
参考商品
最小注文数10個、最短納期5営業日から注文できます。
まとめ
大ロット生産は、オリジナルグッズ製作においてコストを抑えながら安定した品質を実現できる効率的な方法です。需要が見込める商品や定番アイテムでは特に効果を発揮し、単価を下げつつスピーディーに大量供給が可能になります。
一方で、在庫リスクやデザイン変更の柔軟性には課題もあるため、大ロット生産を行う際は、販売計画や需要予測をしっかり立てたうえで実施することが重要です。大量生産ならではのスケールメリットを活かしつつ、無駄を抑えたバランスの取れた生産体制が成功の鍵といえるでしょう。